今週のお題「現時点で今年買ってよかったもの」
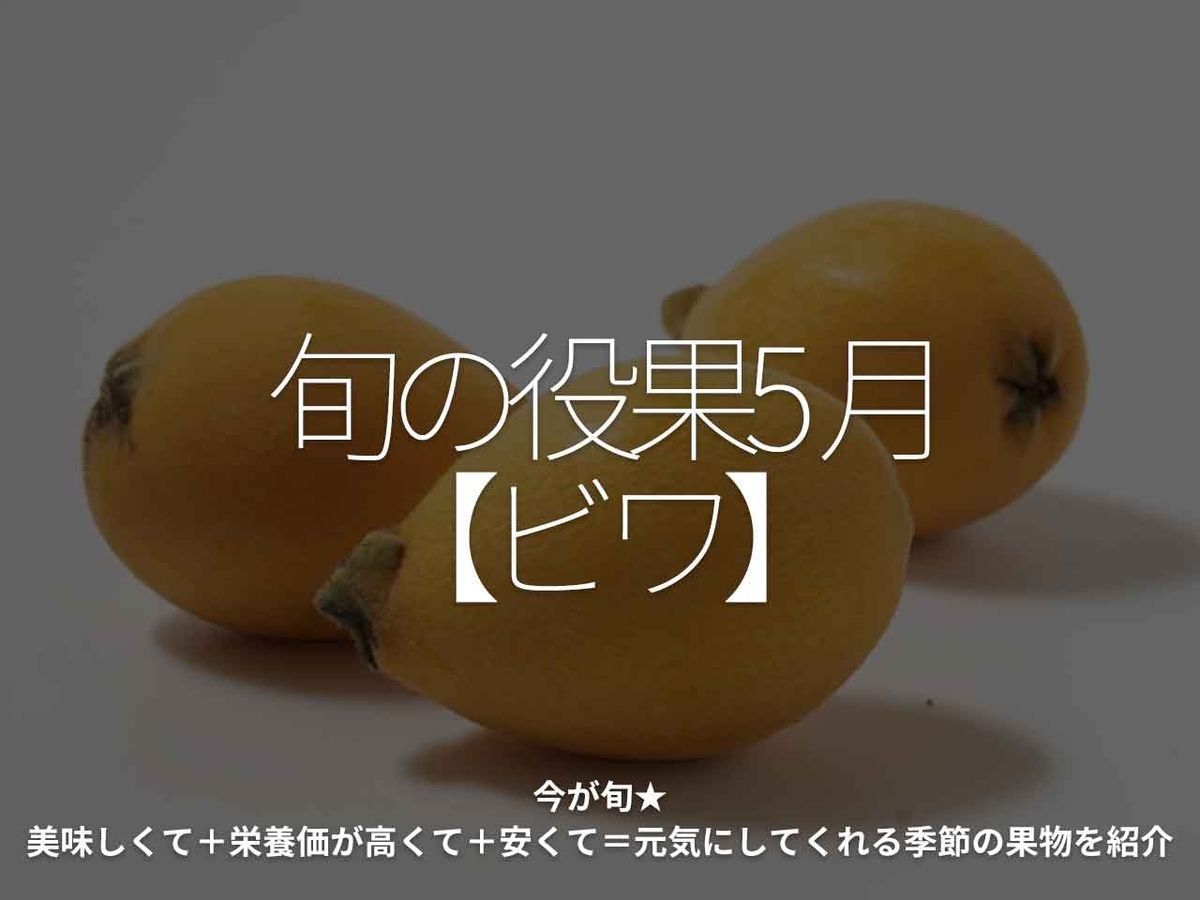
毎月季節の果物を紹介するシリーズ★ その名も「旬の役果」。
私は健康なカラダづくりに役立つ果物を【役果やくか】と呼んでいます。季節ごとに旬を迎える果物たちが持つ特徴的な栄養や成分を充分に引きだして美味しく楽しく頂きましょう。5月の役果はビワです。

ビワ
ビワの旬は5月から8月頃です。

ビワ(枇杷、学名: Rhaphiolepis bibas; シノニム: Eriobotrya japonica)
バラ科の常緑高木、および食用となるその実。原産地は中国南西部。葉は濃い緑色で大きく、長い楕円形をしており、表面にはつやがあり、裏には産毛がある。初夏、その大きな葉陰に楽器の琵琶に似た形をした一口大の多くの甘い実がなり、黄橙色に熟す。日本では四国、九州に帰化植物として自生する。環境省及び農林水産省が作成した生態系被害防止外来種リストでは、産業管理外来種に選定されている。分子系統学的研究を経て、2020年上旬にEriobotrya属とシャリンバイ属(Rhaphiolepis)の区別が否定され、ビワも後者とされたが、この研究に懐疑的な見方も存在する(参照: #分類)。

ビワの名前の由来
「びわ」と聞くと「琵琶湖」をイメージするヒトも多いと思います。果物の「ビワ」の由来とは何でしょう?

和名ビワの語源は、実の形が楽器の琵琶に似ているからとされる。中国語でも「枇杷」(拼音: pípá; 粤拼: pei4 paa4)と表記するほか、「蘆橘」(拼音: lú jú; 粤拼: lou4 gwat1)とも呼ばれ、英語の「loquat」は後者の広東語発音に由来する。
琵琶(びわ、英語: pipa, 特に日本のものは biwa)
東アジアの有棹(リュート属)弦楽器の一つ。弓を使わず、もっぱら弦(絃)をはじいて音を出す撥弦楽器である。古代において四弦系(曲頚琵琶)と五弦系(直頚琵琶)があり、後者は伝承が廃絶し使われなくなったが、前者は後に中国及び日本においていくつもの種類が生じて発展し、多くは現代も演奏されている。ベトナムにはおそらく明代に伝播した四弦十数柱のものが伝承され、ダン・ティ・バと呼ばれる。なお、広義には阮咸(げんかん)や月琴などのリュート属弦楽器も琵琶に含めることもある。四弦系(曲頚)琵琶は、西アジアのウード、ヨーロッパのリュートと共通の起源を持ち、形もよく似ている。すなわち卵を縦に半分に割ったような形の共鳴胴に棹を付け、糸倉(ヘッド)がほぼ直角に後ろに曲がった特徴的な形である。五弦系(直頚)琵琶はインド起源とされ、糸倉は曲がらず真っすぐに伸びている。正倉院に唯一の現物である「螺鈿紫檀五弦の琵琶」(らでんしたんごげんのびわ、図参照)が保存されている。四弦系(曲頚)琵琶が改良されて五弦となった琵琶も、日本の筑前琵琶などで見られる。
と、言うことは「楽器のビワ」の方が先にあって、その後の「果物のビワ」ということなのでしょうか。ちょっと意外。
ちなみに、

琵琶湖の由来
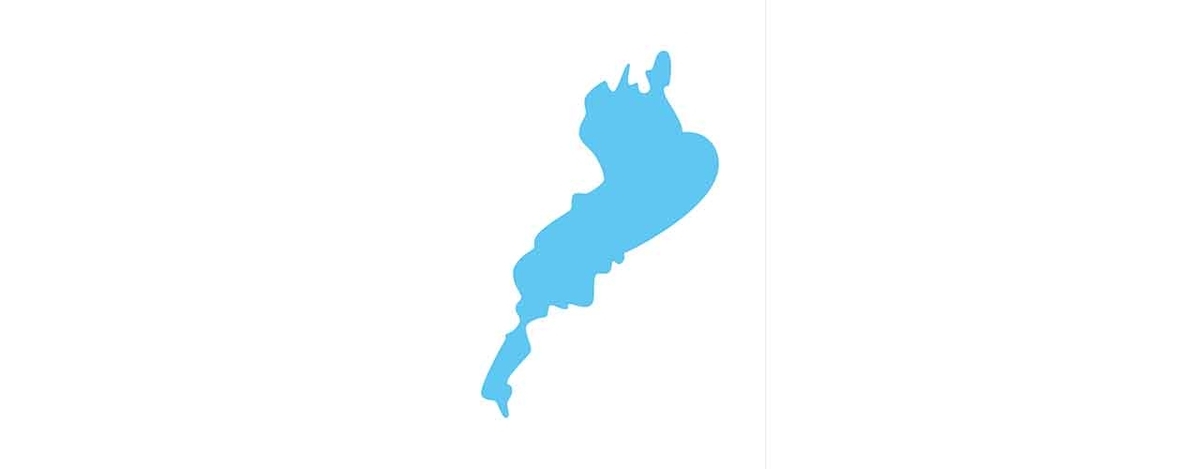
琵琶湖の由来
名前は湖上に浮かぶ竹 生島にまつられている弁才天がもつ楽器の琵琶が湖の形状に似ていることに 由来します。
琵琶湖も楽器のビワが先???琵琶湖の方がそもそもそこにあったはずなのですが。ま、名前を付ける時にちょうどいい「果物のビワ」があった、ということで無理矢理納得。

ビワは中国原産

中国南西部(重慶および湖北省)の原産で、日本には古代に持ち込まれたと考えられており、主に本州の関東地方・東海地方の沿岸、石川県以西の日本海側、四国、九州北部に自然分布する。またインドなどにも広がり、ビワを用いた様々な療法が生まれた。中国系移民がハワイに持ち込んだ他、日本からイスラエルやブラジルに広まった。トルコやレバノン、ギリシャ、イタリア南部、スペイン、フランス南部、アフリカ北部などでも栽培される。日本では江戸時代にビワの栽培が盛んになり、寺の僧侶が檀家の人々に中国から伝わったビワの葉療法を行ったため、寺にはビワの木が多いといわれている。千葉県以南の地域では、庭木として植えられているものもよく見られる。
なんとなくですが、中国原産かなと思いましたが、やはり中国生まれだったようです。

江戸時代の長崎でのビワの話
ビワが日本に入ってきた頃の話。

江戸時代、唯一海外に開かれていた街・長崎。長崎の街には世界各地から様々なものが持ち込まれました。ある時、代官屋敷で働いていた三浦シオという女性が、唐(現在の中国)から持ち込まれたびわの種をもらいました。彼女は茂木の自宅の庭にそっと種を蒔き、大切に育てました。そのびわこそがのちの「茂木びわ」となっていくのです。
長崎びわについて – 長崎びわ -NAGASAKI BIWA
三浦シヲ(本名:荒木ワシ)は、茂木ビワの始祖といわれている。シヲは文政元年(1818)茂木村北浦名元木場に生まれ、長崎で唐ビワ種を入手して茂木にもたらし、茂木にビワが広がったと言われている。なお、唐ビワ種の入手先や伝えた経緯については諸説ある。茂木ビワの沿革については、明治42年(1909)『日本園芸雑誌』の記述に長崎の唐人部屋に出入りする者から茂木にもたらされたとあり、昭和9年(1934)建立の茂木枇杷記念碑において、三浦シヲの名が見られる。長崎市における代表的な産業の一つである「茂木ビワ」生産の始祖として、三浦シヲの名は地域において語り継がれる伝承であり、現在も大切にされている。墓石には「明治三十年旧正月二十日荒木ワシ行年八十才」と刻まれており、茂木ビワの由来に関わる数少ない資料の一つといえる。
指定年月日 令和3年1月5日
所在地 長崎市茂木町2142番地 玉台寺内

ビワの出荷時期
ビワの旬は5月から8月頃です。
と、冒頭でお話しましたが、厳密に3つの出荷時期があります。

- 早生品種:5~7月ごろ
- 中生品種:6~8月ごろ
- 晩生品種:8~9月ごろ
ビワは品種によって出荷時期が異なります。

ビワの品種
ビワの代表的な品種について。

茂木(もぎ)
江戸時代、長崎で一人の女性が唐びわ(中国から輸入された果実)の種子をもらい受け、その種子をまいたことが始まりとされます。長崎市茂木地区で栽培が普及したことからこの名がつきました。長崎県をはじめ西日本で多く栽培されている品種です。長崎早生(ながさきわせ)
寒さに弱いことから、ハウスで栽培されています。 収穫は、早い年には1月にされることもあります。果肉は柔らかく、みずみずしい上品な甘さが特徴です。なつたより
平成21年に品種登録され、大玉で果肉が柔らかくジューシーで、糖度が高いという特徴があります。収穫時期は5月中下旬で、長崎県を中心に栽培が広がっています。田中
明治12年頃に植物学者であった田中芳雄氏が、長崎から東京に持ち帰り育成したのが始まりとされています。果実は大きく、整った釣り鐘型で、果実に光沢があって、完熟すれば甘味と酸味のバランスのとれた品種です。大房(おおぶさ)
千葉県の富浦町で多く生産されている品種で、寒さに強いのが特徴です。果実は大きく、酸味が少なく、ほどよい甘みで果汁も豊富です。

ビワの木は有用
実はビワの「木」自体、とても有用なんだそうです。

ビワの木は粘り強く弾力性があるので、昔から「柿の木から落ちると死ぬが、ビワの木から落ちても死なない」といわれています。
ビワの木で作った木刀は最上のものとされ、農具の柄などにも利用されています。

ビワがよく育つ条件
ビワはどんな環境を好むのでしょうか。

条件① 太陽の光をたっぷり浴びる
太陽の光をいっぱいに浴びせると、成長が良くなるだけでなく、甘くて美味しいびわができます。そのため、日陰がなくて日光が良く当たる場所で栽培するのが重要です。もし、日陰ができてしまったら、周りの葉っぱを伐採して、太陽の光が均等に当たるようにしましょう。条件② 水はけの良い土壌
美味しいびわが育つためには、太陽の光をいっぱいに浴びせるので、こまめな水やりが必須です。水はけが悪いと土の中から腐って根っこがダメになってしまう可能性があるので、水やり後は土が乾くか確認してください。条件③ 気温が大きく変動しない
温暖で気温が一定に保たれており、大きく変動しない環境が理想です。びわは寒さに強いわけではないので、急激に気温が下がると収穫量が減ってしまうケースもあります。ハウス栽培で育てる場合は気温は一定に保たれるので、生産量に大きく影響することはないですが、畑や庭で育てるなら注意が必要です。びわの名産地はどこ?なぜ有名?美味しいびわを産む秘密に迫る! | 産直プライムブログ | JA連携!産地直送通販なら産直プライム
日光がいっぱい当たって、
水がちゃんと吸えて、でも水はけはよくて、
寒くなく、暑すぎることもなく、
温暖な状態が安定しているところ。
・・・ん?ビワって贅沢???

ビワの主な産地
では、どんなところでビワは栽培されているのでしょうか。

ビワの主な産地(2022年)
1 位 長崎県 853トン 33.72 %
2 位 千葉県 417トン 16.48 %
3 位 鹿児島県 189トン 7.47 %
4 位 兵庫県 146トン 5.77 %
5 位 愛媛県 128トン 5.06 %
6 位 香川県 128トン 5.06 %
7 位 大分県 114トン 4.51 %
8 位 和歌山県 47トン 1.86 %
出典:農林水産省統計
長崎県が断トツ!国内のビワの1/3は長崎県産ということのようです。次点は千葉、そして鹿児島、兵庫、、、と、関東以西であれば意外と育つようです。
それぞれの地域には特徴があるようです↓

ビワの三大産地の特徴

【1位】長崎県のびわ栽培の特長
長崎県のびわ栽培の特徴は、気温が高い日が多くて寒暖差が少ないことです。そのため、びわが成長するのに最適な環境が整っており、全国の中でも生産量が多くなっています。長崎県では露地栽培が基本ですが、ハウス栽培も盛んに行われています。【2位】千葉県のびわ栽培の特長
千葉県では、南房総地域を中心にびわ栽培を行っています。首都圏に近く、果樹園も多くあります。また、他のものと比べてサイズが大きくて瑞々しいのが特徴の「房州びわ」を育てています。【3位】鹿児島県のびわ栽培の特長
鹿児島県のびわ栽培の特徴は、気温が非常に高いに高く、びわが成長するのに適した環境が整っていることです。また、肥沃な壌土が多いので、美味しいびわが育ちます。酸味や甘さがあるびわが育ちます。びわの名産地はどこ?なぜ有名?美味しいびわを産む秘密に迫る! | 産直プライムブログ | JA連携!産地直送通販なら産直プライム
長崎県:冬でもびわが栽培でき、品質が高くさまざまな種類のびわを作っています。
千葉県:酸味が少ない「大房(おおふさ)」や食感が良い「田中」、タネが入っていないびわの「希房」などの品種が有名です。
鹿児島県:他県に比べて気温が高く、酸味が少なくさっぱりとした甘さが特徴。
香川県:湿度や気温が高いのが特徴で、太陽の光をいっぱいに浴びて育つので甘みが強いびわに育ちます。
兵庫県:酸味と甘みのバランスが良い「田中」や果肉が柔らかくて甘い「なつたより」などの品種を栽培しています。

庭のビワを勝手に食べるイキモノとは?!
事件があったそうです↓

ビワは万能薬?!

実、種、葉のすべてが万能薬として利用されていた
ビワの果実に豊富に含まれるβカロテンやβクリプトキサンチンは粘膜や皮膚を強化して湿疹やかゆみの緩和に期待できます。また昔から広く漢方薬や民間療法としてビワを使用されてきました。江戸時代、京都や江戸では乾燥したビワの葉や肉桂、甘茶などの煎じ汁である「枇杷葉湯(びわようとう)」が売られ、夏の風物詩でした。暑気あたり、食中毒の予防に効果があると伝えられています。
せき止めには葉の煎じ液、ビワ茶は風邪の予防効果、あせもにビワ葉湯などです。種は焼酎に漬けた「ビワ焼酎」にします。それでうがいをすれば口内炎や歯槽膿漏にも効果があるといわれています。ビワのすぐれた薬効は、奈良時代のころ仏教伝来とともに伝えられたと言われ「大薬王樹」という言葉があるように、ビワの実、種、葉のすべてが利用されました。
大薬王樹
食用のビワの栽培は江戸時代からですが、薬用には約1500年前の奈良時代に、中国から僧医により伝わってきていました。元をたどれば古代インドの医療術アーユルヴェーダでもまた「大般涅槃経」第9巻「如来性品」にも「大薬王樹、枝葉根茎ともに大薬あり、病者は香を嗅ぎ手に触れ、舌に嘗めて悉く諸苦を治す」「譬へば薬樹ありて、名を薬王と曰うが如し。諸薬の中に於いて、最も殊勝為り。(中略)以て創に塗り、身を熏じ、目に塗り、若は見、若は嗅げば、能く衆生の一切の諸病を滅す」と、ビワを「大薬王樹」薬の王様の木であると記され、医療に用いられてきました。これが仏教とともに中国(唐)から日本へと伝わりました。
天平時代、聖武天皇の后である光明皇后が天平2年(730年)、「施薬院」を創設し、病に苦しむ人々の治療のためにビワ葉療法を採用していたのだそう。この時代のビワ葉療法は、ビワの葉を患部に当てるという方法で、これが全国の寺院にビワ療法として広まり、後に陰陽師が治療の際にびわの葉を患部に充てて印を結ぶ呪法や、静岡県の禅寺・金地院ではびわの葉を使った灸療法などが考え出されていきました。かつては薬の王様だった? ビワが旬の季節です(季節・暮らしの話題 2016年05月19日) - 日本気象協会 tenki.jp
王様の薬の樹と言われるほど、当時は薬効が有名だったのでしょう。凄いですね。
「ビワのすぐれた薬効に病人が減ってしまうのを恐れた医者が『ビワの木を庭に植えると病人が出る(不幸になる)』と流布し風説となった」と言われる迷信があります。
これにはいくつかの説があり、病人のいる家で薬代わりに育てていたことが逆説となって「ビワの木は病気になる」と言われたリ、ビワを利用して商売をしていた人が利益を守るために流布したとも言われています。古くからその薬効は認められていたことが分かります。

ビワの主な栄養

ビワ 100g中
- エネルギー・・・・・・・・・・41 kcaL
- たんぱく質・・・・・・・・・・0.3 g
- 脂質・・・・・・・・・・・・・0.1 g
- 炭水化物・・・・・・・・・・・10.6 g
食物繊維・・・・・・・・・・1.6 g- カリウム・・・・・・・・・・・160 mg
- βカロテン・・・・・・・・・・510 μg
- βクリプトキサンチン・・・・・600 μg
- ビタミンB1・・・・・・・・・・0.02 mg
- ビタミンB2・・・・・・・・・・0.03 mg
※参照:「日本食品標準成分表2020年版(八訂)」

ビワの注目したい栄養素

β-カロテン
β-カロテンは、強い抗酸化作用があることで知られています。カロテンは脂溶性であることから、油類といっしょに摂取した方が吸収されやすいため、調理方法を工夫することをおすすめします。β-クリプトキサンチン
クリプトキサンチンは、人の血液中に存在する主要カロチノイドの一つです。これまでの国内外の研究により、β-クリプトキサンチンがいくつかの種類のガン、糖尿病、関節リウマチ、動脈硬化等の発生リスクを低下させる可能性があることが示されてきました。カリウム
人体に必要なミネラルの一種で、体内でナトリウムとともに浸透圧の調節に働きます。ナトリウムの排出を手助けする作用があるため、塩分のとりすぎを調節してくれる効果があります。ビタミンB1
ビタミンB₁は水溶性のビタミンの一種で、糖質をエネルギーに変える際に必要とされるビタミンです。ビタミンB2
ビタミンB2は、ビタミンB1と同様に水溶性のビタミンの一種です。主に脂質のエネルギー代謝に関与し、エネルギーにかわる際に補酵素として働く栄養素です。

★にょろにょろポイント★

種は絶対食べない
びわの種の中心部「仁(じん)」には「アミグダリン」という有害物質が含まれています。アミグダリンは体内で分解されると「青酸(せいさん)」という毒性の高い物質が発生します。青酸を多量に摂取すると頭痛やめまい、嘔吐などの中毒症状を起こし、最悪の場合は死に至ることもあるため、絶対に食べないようにしましょう。【保存版】管理栄養士監修!びわの栄養価と期待できる効果を徹底解説!食べる際の注意点もご紹介 | JA長崎せいひ公式オンラインショップ|長崎県の特産品のお取り寄せ
ビワの種にはアミグダリンという青酸を含む天然の有害物質が含まれています。一時期「ビタミンB17」などと呼ばれがんに効果があると誤解されていましたが、今は明確に否定されており、アミグダリンの健康効果をうたう情報については科学的に十分な根拠はありません。日本では農林水産省も食べないように注意喚起しています。また、アメリカではFDA(米国食品医薬品局)によりアミグダリンの販売は禁止されており、アミグダリンがめまい、頭痛、嘔吐(おうと)などを引き起こす危険性があると言われています。葉にもアミグダリンが含まれているため、一度に大量に摂取しないよう注意が必要です。

ビワはその昔「薬」として扱われた歴史があるように身体にとってよい成分が含まれているようですが、くれぐれも「種」は食べないように注意しましょう!
ビワ、見かけたらぜひお楽しみください。
ー 適 材 適 食 ーてきざいてきしょく
小園 亜由美 (こぞのあゆみ)
管理栄養士・野菜ソムリエ上級プロ・健康運動指導士・病態栄養専門管理栄養士・日本化粧品検定1級

*1:文中の表現は全ての人が対象ではない場合があります。現在治療中の方は必ず担当医や管理栄養士の指示に従ってください。食事療法は医療行為です。ひとりひとりの身体の状態に合わせた適切でオーダーメイドなカウンセリングが必要です。充分に注意してください。
