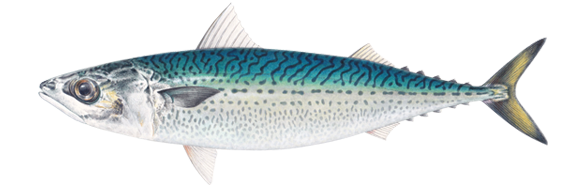今週のお題「マイ流行語」

毎月季節の魚介を紹介するシリーズ★ その名も「旬の役魚」。
私は健康なカラダづくりに役立つ海の幸・魚介類を【役魚やくぎょ】と呼んでいます。季節ごとに旬を迎える魚たちが持つ特徴的な栄養や成分を充分に引きだして美味しく楽しく頂きましょう。12月の役魚はサバです。

サバ
日本でサバと言えば「マサバ」。マサバの旬は晩秋から2月、中でも
10月から11月を「秋サバ」、
12月から2月を「寒サバ」
と呼びます。

サバ(鯖、青花魚、鮄、英: Mackerel)
スズキ目・サバ科のサバ属(Scomber)・グルクマ属(Rastrelliger)・ニジョウサバ属(Grammatorcynus)などに分類される魚の総称。世界各地で食される。日本近海ではマサバ(真鯖)、ゴマサバ、グルクマ、ニジョウサバ(二条鯖)の計4種が見られる。
国内に於いて、サバは大きく分けて3種類です。それぞれを観ていきましょう。

マサバ
マサバは、晩秋から2月ごろにかけてがもっとも脂がのっておいしい時期です。10〜11月ごろのものを「秋サバ」、12〜2月ごろのものを「寒サバ」と呼び、それぞれ秋や冬の風物詩となっています。日本各地で獲れたマサバは、ご当地の「ブランドサバ」として出荷されます。
「サバ」と言ったら大抵の場合「マサバ」の事が多いです。

ゴマサバ
マサバに比べて脂質が少なく、あっさりとした味わいのゴマサバ。1年を通して脂ののりがあまり変わらないので、季節を問わずおいしく食べることができます。
ゴマサバっていうと胡麻のタレがかかったサバと思ってしまいますが、そもそもゴマサバという名前のサバなんです。

タイセイヨウサバ
サバの中でもとくに脂ののりが良いタイセイヨウサバ。マサバ以上に脂質が多く、ゴマサバと同様1年を通してあまり味の変わらない種類です。ノルウェーやカナダなどが原産で、干物や加工品の多くにこのノルウェー産のサバが使われています。
タイセイヨウサバの中でもノルウェー産のものを「ノルウェーサバ」と呼びます。

ブランドサバ
ご当地のブランドサバがあります。ほとんど「マサバ」です。ここでは3種類紹介します。
お嬢サバ
お嬢サバは、JR西日本と鳥取県岩美町の共同研究により生まれた完全養殖のマサバです。地下の海水を使って養殖することで、青魚特有の臭みが少なく、上質な脂が味わえる特徴があります。また、食中毒の原因となるアニサキスを防ぐこともでき、生でも安心して食べることができる鯖です。鯖の旬はいつ?種類によって変わる旬の時期と正しい保存法、美味しい食べ方をご紹介 | ふるなび公式ブログ ふるさと納税DISCOVERY
唐津Qサバ
唐津Qサバは、佐賀県唐津市と九州大学の共同研究により生まれた完全養殖のマサバです。唐津Qサバは完全養殖のため、天然の鯖で発見されるアニサキスという寄生虫が発生する確率が低く、安全に美味しく食べることができます。また、鮮度が落ちやすいと言われている鯖ですが、唐津Qサバは活魚のまま出荷できるため、刺身として食べることも可能です。
鯖の旬はいつ?種類によって変わる旬の時期と正しい保存法、美味しい食べ方をご紹介 | ふるなび公式ブログ ふるさと納税DISCOVERY
金華サバ
金華サバは、宮城県南三陸町の金華山周辺海域で漁獲されるマサバのことです。一般的なマサバと比べると、サイズが大きく、臭みがなく、旨味が強い品種となっており、脂の含有量が多いという特徴があります。金華サバは、厳しい基準をクリアしないと認定されないため、1尾につき1〜3万円の値打ちがつく、非常に希少性の高いブランド鯖です。鯖の旬はいつ?種類によって変わる旬の時期と正しい保存法、美味しい食べ方をご紹介 | ふるなび公式ブログ ふるさと納税DISCOVERY
この中で金華サバについては以前東北へ行った時、サバの缶詰生産工場へお邪魔したことがあります。
金華サバ、とても美味しかったです!これまでに食べた缶詰のサバの中で1番美味しかったです!

サバ=鯖=青魚
サバは漢字で「鯖」。さかなへんに青と書きます。文字通り青魚です。ところで青魚ってどんな魚なのでしょう?

青魚(あおざかな、あおうお)
食用魚のうちイワシ類・サバ類・サンマなどの、いわゆる「背の青い魚」の総称で、日本文化圏での風俗的分類である。青背の魚、青物(あおもの)とも言う。
背中が青い魚のことを青魚と呼ぶそうです。さらに詳しい説明をみると↓
青魚の特徴
主に外観や肉質から見た便宜上・実用上の概念であり、分類学上のまとまった集団ではない。例えば、マイワシはニシン目ニシン科、サンマはダツ目サンマ科、マアジはスズキ目アジ科、サバ類はスズキ目サバ科にそれぞれ属し、互いの間に直接の類縁関係はない。共通する特徴としては以下のようなものがあげられる。
- ほぼ例外なく海産である。(ただしニシンの一部などには湖沼産のものもある。)
- 多くの場合表層近くを群れで遊泳し、大規模な回遊を行う種も多い。
- 比較的食物連鎖の下位に位置する種が多く、プランクトンなどを主な餌とする。
- 名前の通り、背中が青または黒で腹側が白い体色を持つものが多い。これは、表層近くを遊泳する魚種に広く見られる保護色の一種である。
※以上のような生態上の共通点は、以下に示す利用上の共通点と関連している。つまり「青魚」とは収斂進化の結果生じた一種の多系統群とも言える。
筋肉は遊泳に適した赤身で、ヒスチジンなどが多く含まれ、鮮度の低下が早い。含まれる脂質はエイコサペンタエン酸やドコサヘキサエン酸などの不飽和脂肪酸の比率が高く、血中の悪玉コレステロールを減少させるなどの効果があると言われる一方で、酸敗しやすく品質の劣化(いわゆる「油焼け」)を起こしやすい。
比較的小型で大量に漁獲され単価の安い、いわゆる大衆魚を指すことが多い。肉質や外観が似ていても、マグロやブリなどの大型魚や高級魚は、あまり「青魚」とは呼ばれない傾向がある。
上記のような共通の性質があるため、利用法も共通する部分が多いが、詳細は関連項目および各魚種についての項目を参照のこと。
魚でも特に傷みやすいといわれているのは、サバを始めとする青魚、俗に言う光り物だ。サバは体内にほかの魚より多くの酵素を持っているので、酵素によるたんぱく質の分解が早く、腐敗までもあっという間である。足の早い魚はとにかく早めに処理して、酵素で分解される前に食べきるようにしたいものだ。
サバを含む青魚は足が早いと言いますが、腐敗しやすい理由はしっかり科学的に証明されているんですね。サバを缶詰にするというのは理に適っているんですね。

ところで、足が早いという表現をするのでしょうか。

「足が早い」の意味

なぜ魚が腐ることを足が早いというのかには諸説あるようです。そのうちのひとつを紹介します↓
船用語?海の男説
昔から漁師の間では、船の能力を表すときに「足」を使っていた。櫂力があり速く進む船を「足が強い船」といい、構造がもろくて速度の遅い船は「足が弱い船」と言ったのだという。漁で獲れる魚の鮮度にもこの表現が定着し、鮮度がすぐ落ちる魚のことを「足が早い」と表現するようになったという説がある。魚は総じて日持ちしないため、鮮度が落ちないことを「足が遅い」とは表現しないようだ。
もともとは「足が強い船」から転じて「足が早い」となったというのはとても納得いきますね。
ちなみに「早い」と「速い」の違いは、
- 早い・・・・一定の時間よりも前に行うこと
- 速い・・・・一定の時間内の動作の多さ
ということのようです。

サバの栄養

マサバ(生)可食部100gあたり
- エネルギー・・・・・・・・211 kcaL
- たんぱく質・・・・・・・・20.6 g
- 脂質・・・・・・・・・・・16.8 g
- 炭水化物・・・・・・・・・0.3 g
- 鉄分・・・・・・・・・・・1.2 mg
- EPA・・・・・・・・・・・690 mg
- DHA・・・・・・・・・・・970 mg
体を作るもとになる!たんぱく質
サバは必須アミノ酸がバランスよく含まれている良質なたんぱく源です。必須アミノ酸は体内で作ることができないので、必ず食事から摂取する必要があります。たんぱく質は筋肉や内臓、骨、皮膚、髪の毛、血液などを作るもとになります。これらは毎日新しく作られているので毎日摂取することが大切です。EPA(エイコサペンタエン酸)
魚油に多く含まれているn-3系脂肪酸の一種で、血栓の予防や高血圧の予防に効果が期待できます。さらに、善玉コレステロールを増加させて、悪玉コレステロールや中性脂肪を減らす効果も期待できます。DHA(ドコサヘキサエン酸)
こちらも魚油に多く含まれているn-3系脂肪酸の一種です。血流をよくする働きがあり、動脈硬化の予防改善効果が期待できます。また、脳を活性化させて記憶力をよくする効果があり、認知症の予防改善にも効果が期待できます。カルシウムの吸収を助ける!ビタミンD
ビタミンDはカルシウムの吸着を高める骨の健康に欠かせない栄養素です。免疫力をアップする効果も期待できます。魚介類やきのこ類に多く含まれています。貧血予防に効果的!鉄
鉄は酸素を全身に運ぶ赤血球を作るために欠かせないミネラルです。また、筋肉内に酸素を取り込む働きもあり、不足すると酸素を上手く取り込めずに筋力低下や疲労を起こす原因にもなります。体内で吸収されにくい栄養素のひとつですが、ビタミンCを含む食材と一緒にとることで吸収率がアップします。味覚を正常に保つ!亜鉛
亜鉛には細胞を作り成長を促す働きがあり、美しい肌や髪を保つためにも欠かせない栄養素です。また、インスリンや性ホルモンの合成にも関わっています。さらに、亜鉛は舌の表面の味蕾にある味を感じる細胞を作る働きがあり、不足すると味覚異常の原因になります。
特にサバを含む青魚にはEPAとDHAが多く含まれています。

サバの缶詰の栄養
缶詰になったサバの栄養ってどうなっているのでしょう。サバと言えば水煮と味噌煮が二強ですね。
水煮(みずに)
食材を水または塩水で煮ること、または煮たものを指す言葉。主に食材の下拵えや保存のために行われる。購入して味付けするだけで簡単に料理が作れることから、一般家庭はもとより食品加工業や外食産業においても大量に消費されている。
味噌煮(みそに)
味噌を入れて煮ること。また、そのもの。みそだき。

サバの水煮の栄養
まずは缶詰ではなくそのままのサバを調理した時の平均的な栄養価です↓
マサバの水煮(可食部100gあたり)
- エネルギー・・・・・・・253kcal
- たんぱく質・・・・・・・22.6g
- 脂質・・・・・・・・・・22.6g
- 炭水化物・・・・・・・・0.3g
- 鉄分・・・・・・・・・・1.3mg
- EPA・・・・・・・・・・930mg
- DHA・・・・・・・・・・1400mg
ゴマサバの水煮(可食部100gあたり)
- エネルギー・・・・・・・139kcal★
- たんぱく質・・・・・・・24.8g★
- 脂質・・・・・・・・・・5.2g★
- 炭水化物・・・・・・・・0.2g
- 鉄分・・・・・・・・・・1.8mg★
- EPA・・・・・・・・・・230mg
- DHA・・・・・・・・・・8200mg
タイセイヨウサバの水煮(可食部100gあたり)
- エネルギー・・・・・・・310kcal
- たんぱく質・・・・・・・18.6g
- 脂質・・・・・・・・・・28.5g
- 炭水化物・・・・・・・・0.4g★
- 鉄分・・・・・・・・・・1.0mg
- EPA・・・・・・・・・・1600mg★
- DHA・・・・・・・・・・2300mg★
▲マサバ、ゴマサバ、タイセイヨウサバの3種類で最も優れた数値には★をつけました。
サバの水煮の「缶詰」の栄養
サバを調理し缶詰にした時の平均的な栄養価です↓缶詰の場合の数値は【】内に表示します。
サバの水煮の缶詰(可食部100gあたり)
- エネルギー・・・・・・・253kcal→水煮缶詰【174kcal】
- たんぱく質・・・・・・・22.6g→水煮缶詰【20.9g】
- 脂質・・・・・・・・・・22.6g→水煮缶詰【10.7g】
- 炭水化物・・・・・・・・0.3g→水煮缶詰【0.2g】
- 鉄分・・・・・・・・・・1.3mg→水煮缶詰【1.6mg】
- EPA・・・・・・・・・・930mg→水煮缶詰【930mg】
- DHA・・・・・・・・・・1400mg→水煮缶詰【1300mg】
サバの味噌煮の缶詰(可食部100gあたり)
- エネルギー・・・・・・・253kcal→味噌煮缶詰【210kcal】
- たんぱく質・・・・・・・22.6g→味噌煮缶詰【16.3g】
- 脂質・・・・・・・・・・22.6g→味噌煮缶詰【13.9g】
- 炭水化物・・・・・・・・0.3g→味噌煮缶詰【6.6g】
- 鉄分・・・・・・・・・・1.3mg→味噌煮缶詰【2.0mg】
- EPA・・・・・・・・・・930mg→味噌煮缶詰【1100mg】
- DHA・・・・・・・・・・1400mg→味噌煮缶詰【1500mg】
こうしてみると、そのままなのか缶詰なのか、水煮と味噌煮でも違いますし、サバの種類によっても栄養価が変わってくるのがわかります。
サバを購入する際は「サバの種類」や「缶詰の栄養価」を確認するとよいですね。

鯖を読む
サバは「さばをよむ」ということわざがあります。あまりよい意味ではないですが、なぜ「サバ」なのでしょう。

鯖を読む
物を数えるとき、自分に都合のよいように数をごまかすこと。「読む」は、数える。
[解説] 語源については種々の説があります。
- 魚市で早口で小魚を数えることをイサバヨミ(魚市読)といい、その略。
- 捕獲した大量の鯖を数えるとき、使用人がごまかすところからはじまる。
- 鯖は腐りやすく、急いで売りさばく必要があり、数え方もいいかげんであるところからいった。
- 刺鯖など二枚重ねを一連として数えたところからの転用。
「鯖を読む」 語源
語源は諸説あるが、魚屋がたくさんの鯖をまとめて売るときに、(わざと)数え間違って実数より多く言いがちであることから来たものとする説が有力。魚市場を意味する「五十集いさば」に由来し、市場で小魚を早口で数えることを「五十集読(いさばよみ)」と言っていたのが元であったとの説もある。
折口信夫は魚の鯖の説を否定し、仏教用語の「産飯さば」(そなえものとして盛った飯)から来ているとしている。この説では、「さば」の一部が施しとて撒かれ餓鬼や鳥獣などに与えられるさまから、つまみ食いのことを「さばよみ」と呼ぶようになったとする。
寿司屋が客に寿司を出すとき少量の飯(これを仏教のさばになぞらえた)を飯台の裏につけて数の記録とし後で勘定する行為を「さばを読む」と呼んだのを語源とする説もある。
「さばよみ」の項目も参照。
数量を誤魔化す意味で使われていますが、逆に考えれば、誤魔化せる程「たくさんのサバが一度に獲れた」ということだけは判ります。

▼今まで取り上げたサバに関する記事

★ぴょん!ポイント★

美味しいだけでなく栄養価の高いサバ。足が早い青魚ですが、缶詰を利用することで、いつでも美味しいサバを頂くことができます。旬のサバをぎゅっと詰め込んだ缶詰を美味しく頂きましょう。
ちなみに。
ブリ大根ならぬ、サバ大根も美味しいのでレシピを紹介します↓
ー 適 材 適 食 ーてきざいてきしょく
小園 亜由美 (こぞのあゆみ)
管理栄養士・野菜ソムリエ上級プロ・健康運動指導士・病態栄養専門管理栄養士・日本化粧品検定1級

*1:文中の表現は全ての人が対象ではない場合があります。現在治療中の方は必ず担当医や管理栄養士の指示に従ってください。食事療法は医療行為です。ひとりひとりの身体の状態に合わせた適切でオーダーメイドなカウンセリングが必要です。充分に注意してください。